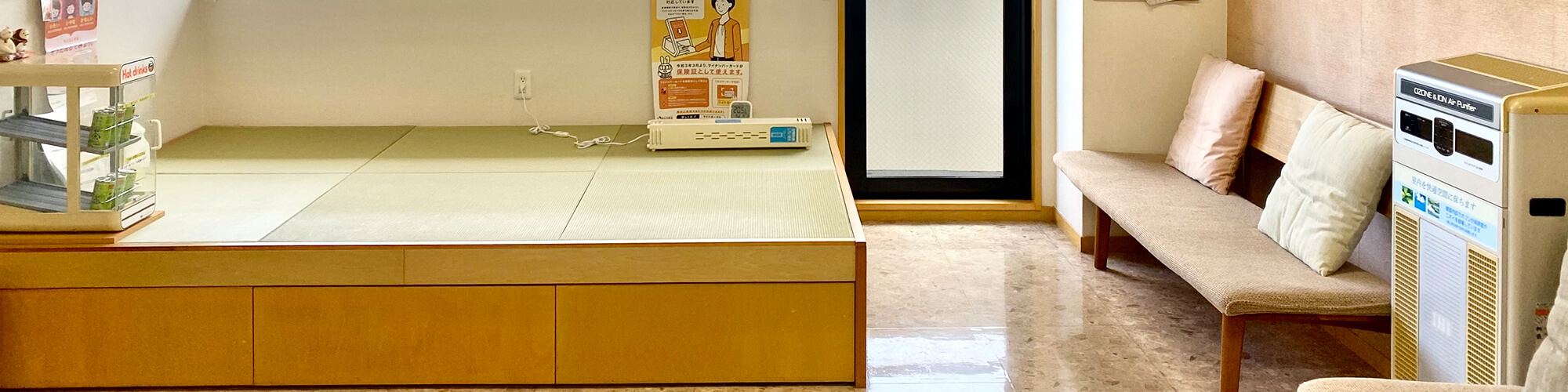
よくある症状
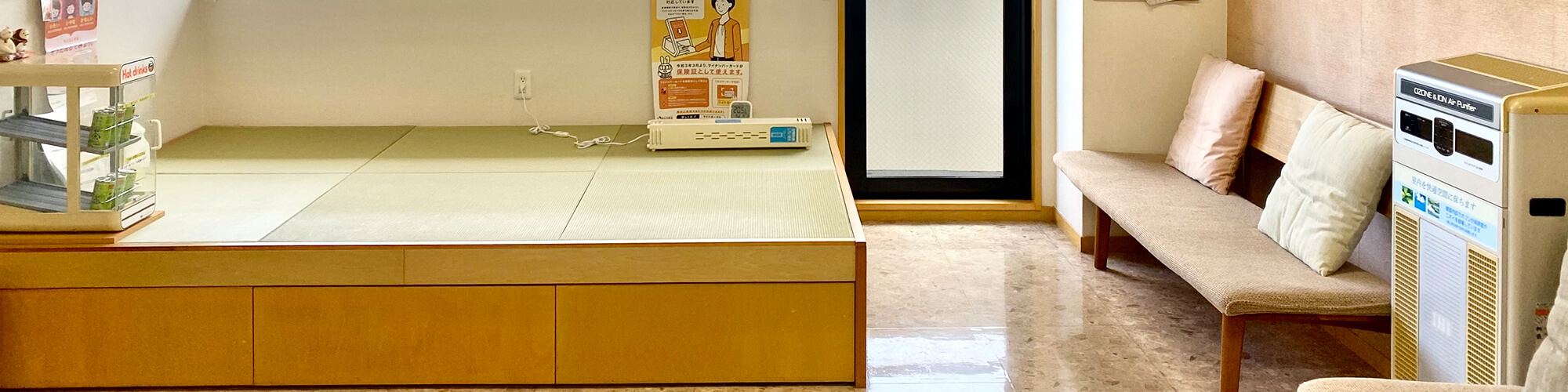
よくある症状
考えられる疾患
尿路結石
腎臓から尿道につながる尿路に結石ができる疾患で、結石のある部位によって腎臓結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分けられます。泌尿器科外来で頻度の高い疾患の一つで、20人に1人が一生に一度は罹患し、男性が女性の約3倍多いとされています。
結石の大きさや位置によっては激痛(腰部・側腹部)が起こり、血尿や吐き気、嘔吐を伴うこともあります。尿検査、画像検査(超音波検査・レントゲン検査・CT検査など)で診断がついたら、まず痛みを抑えます。その後、結石の大きさや位置を確認し、治療方針を検討します。4ミリ以下の小さい結石であれば、薬剤を使い自然に体外に結石が出る排石を待つ保存療法が基本になります。10ミリ以上の大きな結石や、自然排石が難しいと考えられる場合には、体外衝撃波結石破砕手術(ESWL)やレーザー砕石器などを用いた内視鏡手術が行われます。
膀胱炎
女性に多く、頻尿、血尿、排尿時の痛みが特徴的な病気です。多くは排尿の最後のほうや排尿後にしみるような不快な痛みを感じます。悪化してくると残尿感がひどく、何度もトイレに行くようになり、はっきりとした痛みを伴うこともあります。さらに悪化すると、排尿時の焼け付くような痛み、血尿が現れることもあります。膀胱炎は何らかの原因で尿道から細菌が膀胱へ侵入することによって起こります。一番の原因となるのは大腸菌ですが、通常は抗生剤治療で数日以内に完治することがほとんどです。膀胱炎は放っておくと腎盂腎炎(じんうじんえん)を併発してしまうこともありますので、膀胱炎の疑いのある症状が出た場合、早めの受診をお勧めします。
前立腺炎
急性前立腺炎の多くは大腸菌などの細菌が尿道から侵入し、前立腺に感染することで起きますが、血液やリンパ液から細菌が前立腺に侵入して感染する場合もあります。症状としては、高熱(発熱)や排尿困難、排尿痛や残尿感、頻尿、全身倦怠感が生じます。急激に悪化した場合、敗血症などを併発する危険性があるため早期治療が重要です。
慢性前立腺炎は長時間座ったままの姿勢を取り続ける人、働き盛りの20~40代に多いのが特徴です。会陰部の不快感、排尿時排尿後の痛み、射精時射精後の痛み、精液に血が混じるなどの症状が現れます。治療は症状によって異なりますが、症状が改善するまでに数ヶ月かかることもあります。
前立腺がん
前立腺がんは泌尿器系のがんの中で、近年最も増加傾向にあります。かなり進行するまで症状が無いケースがほとんどで、検診がとても重要になります。検診でPSA(前立腺特異抗原)という腫瘍マーカーを測定するようになってからは、早期診断も可能になってきました。
早期発見、治療を行えば死亡率は非常に低いがんです。50歳を超えたら年に1度はPSA検診をお勧めします。
膀胱がん
膀胱がんは、膀胱の内側を覆う粘膜(移行上皮)に発生する悪性腫瘍です。主に膀胱の内壁にがん細胞が増殖し、早期には膀胱内に留まりますが、進行すると膀胱の壁や周囲の臓器、さらにはリンパ節や他の臓器へ転移することもあります。泌尿器系のがんの中でも比較的頻度が高く、特に50歳以上の男性に多く発症します。また、タバコによる喫煙が危険因子と言われており、がんのリスクを高めます。
腎臓がん
腎臓がんは、腎臓の細胞が異常に増殖し、腫瘍を形成する病気です。腎臓は、体内の老廃物や余分な水分を血液からろ過し、尿を作る重要な臓器です。腎臓がんの中で最も一般的なタイプは腎細胞がんで、腎臓内の尿を作る細胞から発生します。他にも、腎盂(じんう)がんや、腎芽腫(ウィルムス腫瘍)などのタイプがありますが、これらは比較的まれです。
腎臓がんは早期には自覚症状がほとんどないため、定期的な健康診断や画像検査で偶然発見されることが多いです。早期発見・治療が行われれば、治癒の可能性が高いですが、進行すると周囲の臓器や遠隔のリンパ節、さらには肺や骨に転移することもあります。
考えられる疾患
活動性膀胱
膀胱を管理する自律神経が過敏になり、膀胱に尿が十分に貯まっていない段階から、膀胱が勝手に収縮してしまう病気です。頻尿と尿意切迫感(尿が我慢できない)を特徴とし症状がひどい場合は尿漏れを発生します。日本では1000万人以上の男女が罹患するといわれている頻度の高い病気です。脳や脊髄の病気、前立腺肥大症、膀胱炎、加齢、精神的なストレスなど原因は様々ですが、原因がはっきりしないケースも少なくありません。
診療では、他の病気の可能性も含めて、問診や検査(腹部エコー検査、血液検査、尿検査、尿流測定、パッドテスト、ストレステストなど)を行います。生活習慣の見直しで頻尿が改善することも多い病気ですので、薬だけに頼らず生活習慣の見直しや指導も積極的に行っていきます。
膀胱炎
女性に多く、頻尿、血尿、排尿時の痛みが特徴的な病気です。多くは排尿の最後のほうや排尿後にしみるような不快な痛みを感じます。悪化してくると残尿感がひどく、何度もトイレに行くようになり、はっきりとした痛みを伴うこともあります。さらに悪化すると、排尿時の焼け付くような痛み、血尿が現れることもあります。膀胱炎は何らかの原因で尿道から細菌が膀胱へ侵入することによって起こります。一番の原因となるのは大腸菌ですが、通常は抗生剤治療で数日以内に完治することがほとんどです。膀胱炎は放っておくと腎盂腎炎(じんうじんえん)を併発してしまうこともありますので、膀胱炎の疑いのある症状が出た場合、早めの受診をお勧めします。
尿路結石
結石の大きさや位置によっては激痛が起こり、発熱や吐き気、嘔吐を伴うこともあります。尿検査、画像検査(超音波検査・レントゲン検査・CT検査など)で診断がついたら、まず痛みを抑えます。その後、結石の大きさや位置を確認し、治療方針を検討します。4ミリ以下の小さい結石であれば、薬剤を使い自然に体外に結石が出る排石を待つ保存療法が基本になります。10ミリ以上の大きな結石や、自然排石が難しいと考えられる場合には、体外衝撃波結石破砕手術(ESWL)やレーザー砕石器などを用いた内視鏡手術が行われます。
膀胱がん
膀胱がんは、膀胱の内側を覆う粘膜(移行上皮)に発生する悪性腫瘍です。主に膀胱の内壁にがん細胞が増殖し、早期には膀胱内に留まりますが、進行すると膀胱の壁や周囲の臓器、さらにはリンパ節や他の臓器へ転移することもあります。泌尿器系のがんの中でも比較的頻度が高く、特に50歳以上の男性に多く発症します。また、タバコによる喫煙が危険因子と言われており、がんのリスクを高めます。
前立腺肥大症
前立腺肥大症は、前立腺の病気のなかで最も頻度の高い病気です。前立腺が肥大して様々な排尿障害が生じてきます。前立腺は直腸と恥骨の間にあり、尿道を取り囲んでいます。そのため前立腺が肥大すると、尿道を圧迫して排尿に関わる症状が現れます。一般的な成人男性の前立腺は、クルミぐらいの大きさと例えられますが、肥大すると林檎や鶏卵ぐらいの大きさになります。
症状としては、夜中に何度もトイレのために起きたり(夜間頻尿)、排尿までに時間がかかったり(排尿困難)、尿線が細くなります。さらに進行すると尿が全く出なくなります(尿閉)。昔は前立腺が大きくなることによってこうした症状が出現すると考えられてきましたが、近年では生活習慣病と前立腺肥大症の相関が報告されています。診断には症状から病気を疑う国際的評価方法(IPSS)や、診察・検査として直腸指診、超音波検査やMRI検査などの画像検査、前立腺癌の腫瘍マーカー検査(採血検査)、残尿測定・尿流量測定があります。治療は薬物療法、手術療法などが主ですが、中間的な治療法として、前立腺高温度治療(前立腺の組織を温めて、組織を変性、縮小させる治療法)があります。
前立腺がん
前立腺がんは泌尿器系のがんの中で、近年最も増加傾向にあります。かなり進行するまで症状が無いケースがほとんどで、検診がとても重要になります。検診でPSA(前立腺特異抗原)という腫瘍マーカーを測定するようになってからは、早期診断も可能になってきました。
早期発見、治療を行えば死亡率は非常に低いがんです。50歳を超えたら年に1度はPSA検診をお勧めします。
前立腺炎
急性前立腺炎の多くは大腸菌などの細菌が尿道から侵入し、前立腺に感染することで起きますが、血液やリンパ液から細菌が前立腺に侵入して感染する場合もあります。症状としては、高熱(発熱)や排尿困難、排尿痛や残尿感、頻尿、全身倦怠感が生じます。急激に悪化した場合、敗血症などを併発する危険性があるため早期治療が重要です。
慢性前立腺炎は長時間座ったままの姿勢を取り続ける人、働き盛りの20~40代に多いのが特徴です。会陰部の不快感、排尿時排尿後の痛み、射精時射精後の痛み、精液に血が混じるなどの症状が現れます。治療は症状によって異なりますが、症状が改善するまでに数カ月かかることもあります。
骨盤臓器脱
加齢の変化で骨盤底の筋肉が弱くなり、子宮や膣壁が正常の位置より病的に下垂する病気です。進行すると膣外に子宮、膣、膀胱、腸管などの臓器が排出される状態になります。更年期以降の女性に認められ、お産経験がある女性の約半数に生じるともいわれています。
軽度では自覚症状がなく、進行すると尿失禁や頻尿、異物感などが生じてきますが、脱出部位により、症状は様々です。治療は体操(骨盤底筋訓練)、ペッサリー(膣内に器具を入れて下垂を抑える)療法、手術療法があり、症状や年齢によって選択されます。
考えられる疾患
膀胱炎
女性に多く、頻尿、血尿、排尿時の痛みが特徴的な病気です。多くは排尿の最後のほうや排尿後にしみるような不快な痛みを感じます。悪化してくると残尿感がひどく、何度もトイレに行くようになり、はっきりとした痛みを伴うこともあります。さらに悪化すると、排尿時の焼け付くような痛み、血尿が現れることもあります。膀胱炎は何らかの原因で尿道から細菌が膀胱へ侵入することによって起こります。一番の原因となるのは大腸菌ですが、通常は抗生剤治療で数日以内に完治することがほとんどです。膀胱炎は放っておくと腎盂腎炎(じんうじんえん)を併発してしまうこともありますので、膀胱炎の疑いのある症状が出た場合、早めの受診をお勧めします。
活動性膀胱炎
膀胱を管理する自律神経が過敏になり、膀胱に尿が十分に貯まっていない段階から、膀胱が勝手に収縮してしまう病気です。頻尿と尿意切迫感(尿が我慢できない)を特徴とし症状がひどい場合は尿漏れを発生します。日本では1000万人以上の男女が罹患するといわれている頻度の高い病気です。脳や脊髄の病気、前立腺肥大症、膀胱炎、加齢、精神的なストレスなど原因は様々ですが、原因がはっきりしないケースも少なくありません。
診療では、他の病気の可能性も含めて、問診や検査(腹部エコー検査、血液検査、尿検査、尿流測定、パッドテスト、ストレステストなど)を行います。生活習慣の見直しで頻尿が改善することも多い病気ですので、薬だけに頼らず生活習慣の見直しや指導も積極的に行っていきます。
子宮脱
加齢の変化で骨盤底の筋肉が弱くなり、子宮や膣壁が正常の位置より病的に下垂する病気です。進行すると膣外に子宮、膣、膀胱、腸管などの臓器が排出される状態になります。更年期以降の女性に認められ、お産経験がある女性の約半数に生じるともいわれています。
前立腺肥大症
前立腺肥大症は、前立腺の病気のなかで最も頻度の高い病気です。前立腺が肥大して様々な排尿障害が生じてきます。前立腺は直腸と恥骨の間にあり、尿道を取り囲んでいます。そのため前立腺が肥大すると、尿道を圧迫して排尿に関わる症状が現れます。一般的な成人男性の前立腺は、クルミぐらいの大きさと例えられますが、肥大するとみかんや卵ぐらいの大きさになります。
症状としては、夜中に何度もトイレのために起きたり(夜間頻尿)、排尿までに時間がかかったり(排尿困難)、尿線が細くなります。さらに進行すると尿が全く出なくなります(尿閉)。昔は前立腺が大きくなることによってこうした症状が出現すると考えられてきましたが、近年では生活習慣病と前立腺肥大症の相関が報告されています。診断には症状から病気を疑う国際的評価方法(IPSS)や、診察・検査として直腸指診、超音波検査やMRI検査などの画像検査、前立腺癌の腫瘍マーカー検査(採血検査)、残尿測定・尿流量測定があります。治療は薬物療法、手術療法などが主ですが、中間的な治療法として、前立腺高温度治療(前立腺の組織を温めて、組織を変性、縮小させる治療法)があります。
考えられる疾患
前立腺炎
急性前立腺炎の多くは大腸菌などの細菌が尿道から侵入し、前立腺に感染することで起きますが、血液やリンパ液から細菌が前立腺に侵入して感染する場合もあります。症状としては、高熱(発熱)や排尿困難、排尿痛や残尿感、頻尿、全身倦怠感が生じます。急激に悪化した場合、敗血症などを併発する危険性があるため早期治療が重要です。
慢性前立腺炎は長時間座ったままの姿勢を取り続ける人、働き盛りの20~40代に多いのが特徴です。会陰部の不快感、排尿時排尿後の痛み、射精時射精後の痛み、精液に血が混じるなどの症状が現れます。治療は症状によって異なりますが、症状が改善するまでに数カ月かかることもあります。
膀胱炎
女性に多く、頻尿、血尿、排尿時の痛みが特徴的な病気です。多くは排尿の最後のほうや排尿後にしみるような不快な痛みを感じます。悪化してくると残尿感がひどく、何度もトイレに行くようになり、はっきりとした痛みを伴うこともあります。さらに悪化すると、排尿時の焼け付くような痛み、血尿が現れることもあります。膀胱炎は何らかの原因で尿道から細菌が膀胱へ侵入することによって起こります。一番の原因となるのは大腸菌ですが、通常は抗生剤治療で数日以内に完治することがほとんどです。膀胱炎は放っておくと腎盂腎炎(じんうじんえん)を併発してしまうこともありますので、膀胱炎の疑いのある症状が出た場合、早めの受診をお勧めします。
前立腺炎
急性前立腺炎の多くは大腸菌などの細菌が尿道から侵入し、前立腺に感染することで起きますが、血液やリンパ液から細菌が前立腺に侵入して感染する場合もあります。症状としては、高熱(発熱)や排尿困難、排尿痛や残尿感、頻尿、全身倦怠感が生じます。急激に悪化した場合、敗血症などを併発する危険性があるため早期治療が重要です。
慢性前立腺炎は長時間座ったままの姿勢を取り続ける人、働き盛りの20~40代に多いのが特徴です。会陰部の不快感、排尿時排尿後の痛み、射精時射精後の痛み、精液に血が混じるなどの症状が現れます。治療は症状によって異なりますが、症状が改善するまでに数カ月かかることもあります。
前立腺肥大症
前立腺肥大症は、前立腺の病気のなかで最も頻度の高い病気です。前立腺が肥大して様々な排尿障害が生じてきます。前立腺は直腸と恥骨の間にあり、尿道を取り囲んでいます。そのため前立腺が肥大すると、尿道を圧迫して排尿に関わる症状が現れます。一般的な成人男性の前立腺は、クルミぐらいの大きさと例えられますが、肥大するとみかんや卵ぐらいの大きさになります。
症状としては、夜中に何度もトイレのために起きたり(夜間頻尿)、排尿までに時間がかかったり(排尿困難)、尿線が細くなります。さらに進行すると尿が全く出なくなります(尿閉)。昔は前立腺が大きくなることによってこうした症状が出現すると考えられてきましたが、近年では生活習慣病と前立腺肥大症の相関が報告されています。診断には症状から病気を疑う国際的評価方法(IPSS)や、診察・検査として直腸指診、超音波検査やMRI検査などの画像検査、前立腺癌の腫瘍マーカー検査(採血検査)、残尿測定・尿流量測定があります。治療は薬物療法、手術療法などが主ですが、中間的な治療法として、前立腺高温度治療(前立腺の組織を温めて、組織を変性、縮小させる治療法)があります。
活動性膀胱
膀胱を管理する自律神経が過敏になり、膀胱に尿が十分に貯まっていない段階から、膀胱が勝手に収縮してしまう病気です。頻尿と尿意切迫感(尿が我慢できない)を特徴とし症状がひどい場合は尿漏れを発生します。日本では1000万人以上の男女が罹患するといわれている頻度の高い病気です。脳や脊髄の病気、前立腺肥大症、膀胱炎、加齢、精神的なストレスなど原因は様々ですが、原因がはっきりしないケースも少なくありません。
診療では、他の病気の可能性も含めて、問診や検査(腹部エコー検査、血液検査、尿検査、尿流測定、パッドテスト、ストレステストなど)を行います。生活習慣の見直しで頻尿が改善することも多い病気ですので、薬だけに頼らず生活習慣の見直しや指導も積極的に行っていきます。
前立腺がん
考えられる疾患
急性精巣上体炎
精巣の上の方に位置する精巣上体に細菌が入り込み炎症を来す病気です。発症すると陰嚢に痛みと腫れを生じ、悪化すると発熱などの症状も現れます。
精巣捻転
精巣への血液供給を行う血管・神経・精管が束ねられた精索が捻れてしまう病気です。
陰嚢部から下腹部にかけての痛みと陰嚢の腫れが生じ、放置すると精巣が壊死に陥る可能性があります。手を使って正常な位置に戻す処置を試みますが、不可の場合は開腹手術となります。6時間以内に手術が勧められます。
陰嚢水腫
陰嚢の中に水がたまった袋があり、陰嚢が大きく膨れる状態になる病気です。基本的に痛みを伴いません。乳児期に多くみられますが1歳ころまでに自然に治癒することが多いとされ、1歳を過ぎると自然治癒がしにくくなるといわれています。ときに鼠径(そけい)ヘルニアと陰嚢水腫の判断は難しいこともありますので、気になることがあれば受診をお勧めします。
精巣がん
精巣がんは、男性の精巣(睾丸)に発生する悪性腫瘍です。精巣は、男性の生殖器官の一部で、精子を作るとともに、男性ホルモン(テストステロン)を分泌する役割を担っています。精巣がんは比較的まれな病気であり、全体のがんの中で占める割合は低いですが、20歳から40歳の若い男性に多く見られる特徴があります。早期発見と治療が可能であれば、治療成績は非常に良好で、完全に治癒することが期待できます。
精索静脈瘤
精巣への血液供給を行う血管・神経・精管が束ねられた精索内の静脈が瘤のように拡張する状態。静脈が腫れて太くなりますが精巣自体は腫れません。陰部の不快感程度はありますが、痛みには至りません。
将来的に男性不妊症の原因となる可能性があります。
緊急性はありませんが一度受診を勧めます。
クラミジア感染症
クラミジア・トラコマチスという細菌による感染症です。男性では尿道からの分泌物や排尿時の痛み、女性ではおりものの増加や下腹部痛などが症状として現れます。放置すると、不妊症の原因になることもあります。
淋菌感染症(淋病)
淋菌による感染症で、男性では尿道炎、女性では膣炎が主な症状です。膿のような分泌物が出たり、排尿時に強い痛みがある場合があります。
ヘルペス
単純ヘルペスウイルスによる感染症で、性器周辺に水疱や潰瘍が現れ、痛みやかゆみを伴います。再発しやすく、免疫力が低下すると症状が現れることがあります。
尖圭コンジローマ
ヒトパピローマウイルス(HPV)で感染することで引き起こされる。
女性であれば外陰部を中心に、男性であれば陰茎などにトサカのような淡紅色~褐色のイボが形成される。
当院では①電気メスでイボを焼き切る治療 ②塗り薬を用いた治療を行っています。
梅毒
梅毒トレポネーマという細菌が原因で、皮膚や粘膜に症状が現れる感染症です。初期には
ペニス環状溝に小さなしこりや潰瘍ができ、放置すると全身に発疹(バラ疹)や炎症が広がります。治療を怠ると深刻な合併症を引き起こします。
HIV感染症/エイズ
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が原因で、免疫システムを破壊する病気です。初期には風邪のような症状が現れることが多く、無症状の期間を経て免疫力が著しく低下することでエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症します。
B型肝炎
B型肝炎ウイルスの感染によって肝機能障害を発症する性感染症(STD)。
ウイルスが持続感染すると慢性肝炎→肝硬変→肝臓がんを発症することがあります。
考えられる疾患
尿路結石
腎臓から尿道につながる尿路に結石ができる疾患で、結石のある部位によって腎臓結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分けられます。泌尿器科外来で頻度の高い疾患の一つで、20人に1人が一生に一度は罹患し、男性が女性の約3倍多いとされています。
結石の大きさや位置によっては激痛が起こり、発熱や吐き気、嘔吐を伴うこともあります。尿検査、画像検査(超音波検査・レントゲン検査・CT検査など)で診断がついたら、まず痛みを抑えます。その後、結石の大きさや位置を確認し、治療方針を検討します。4ミリ以下の小さい結石であれば、薬剤を使い自然に体外に結石が出る排石を待つ保存療法が基本になります。10ミリ以上の大きな結石や、自然排石が難しいと考えられる場合には、体外衝撃波結石破砕手術(ESWL)やレーザー砕石器などを用いた内視鏡手術が行われます。
腎臓がん・腎盂がん・尿管がん
血尿・腰痛~側腹部痛の場合 尿管結石の可能性が高いですが、腎臓~尿管のがんでも同様の症状を示すことがあります。
CT等のレントゲン検査を行い確実に診断する事をお勧めします。
当院では、検診で「血尿・蛋白尿・膿尿」が出たとの結果が出た場合再検査をおこなっております。
「尿が泡立つ」「尿に嫌な匂いがする」など些細なことでもお気軽にご相談ください。
TOP